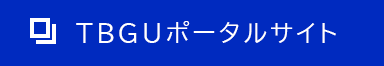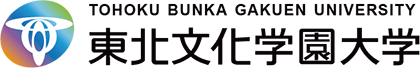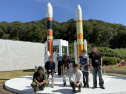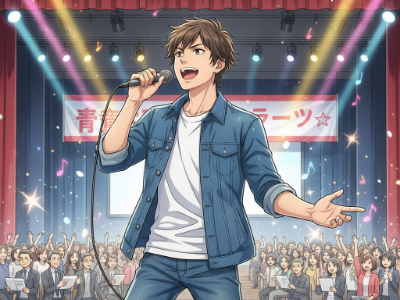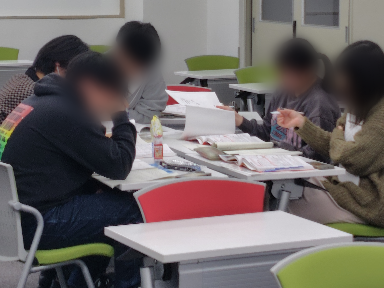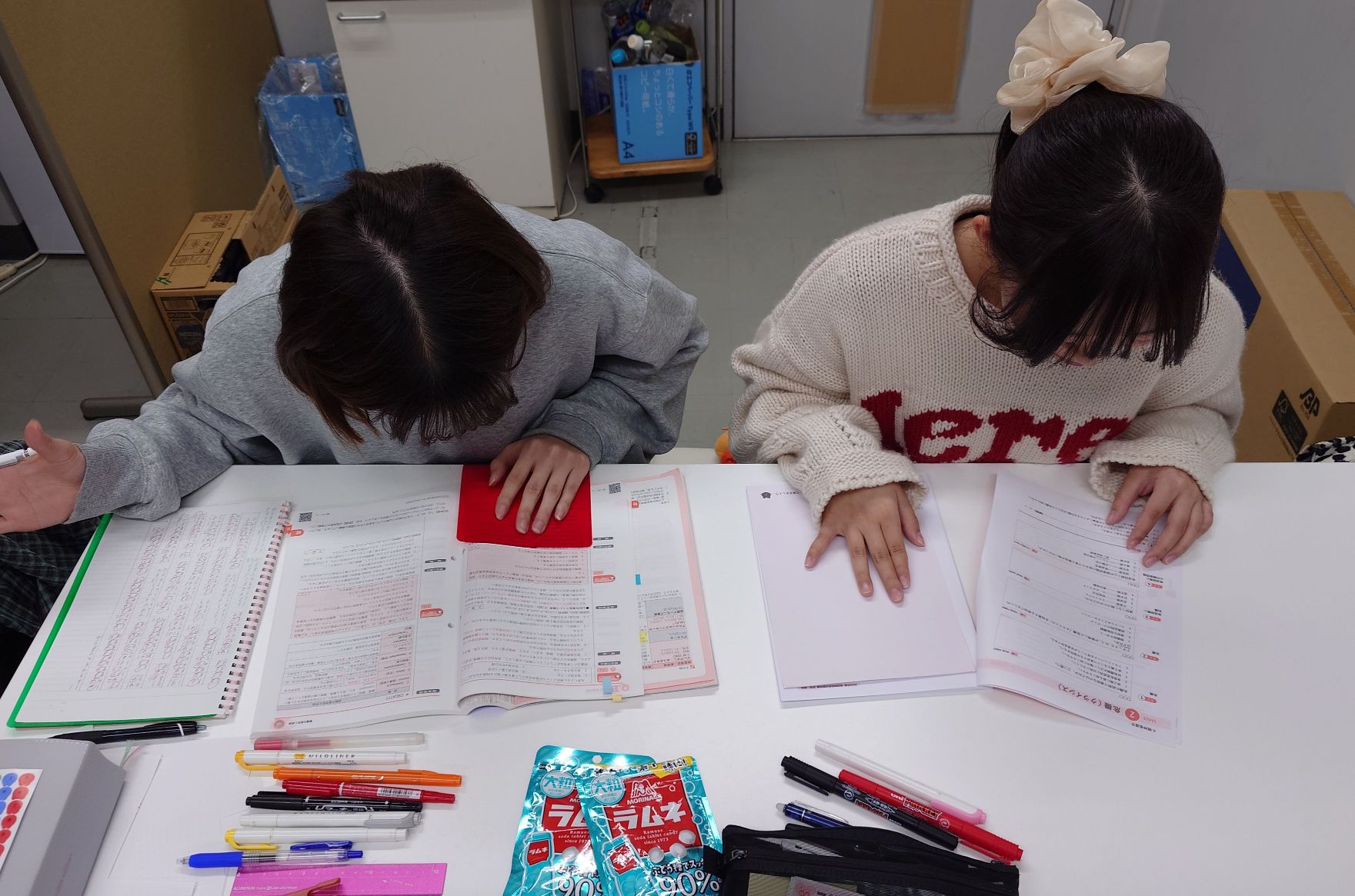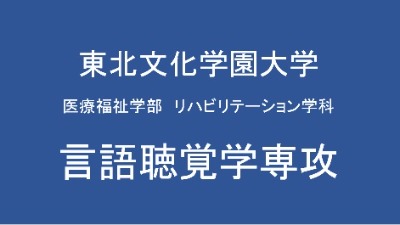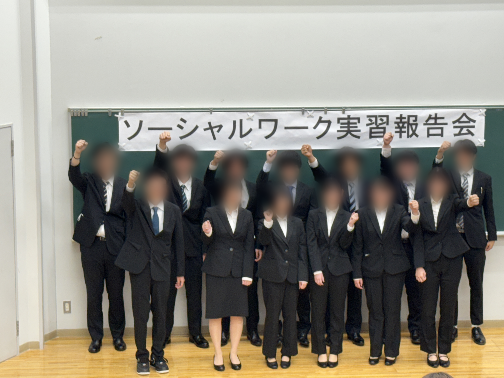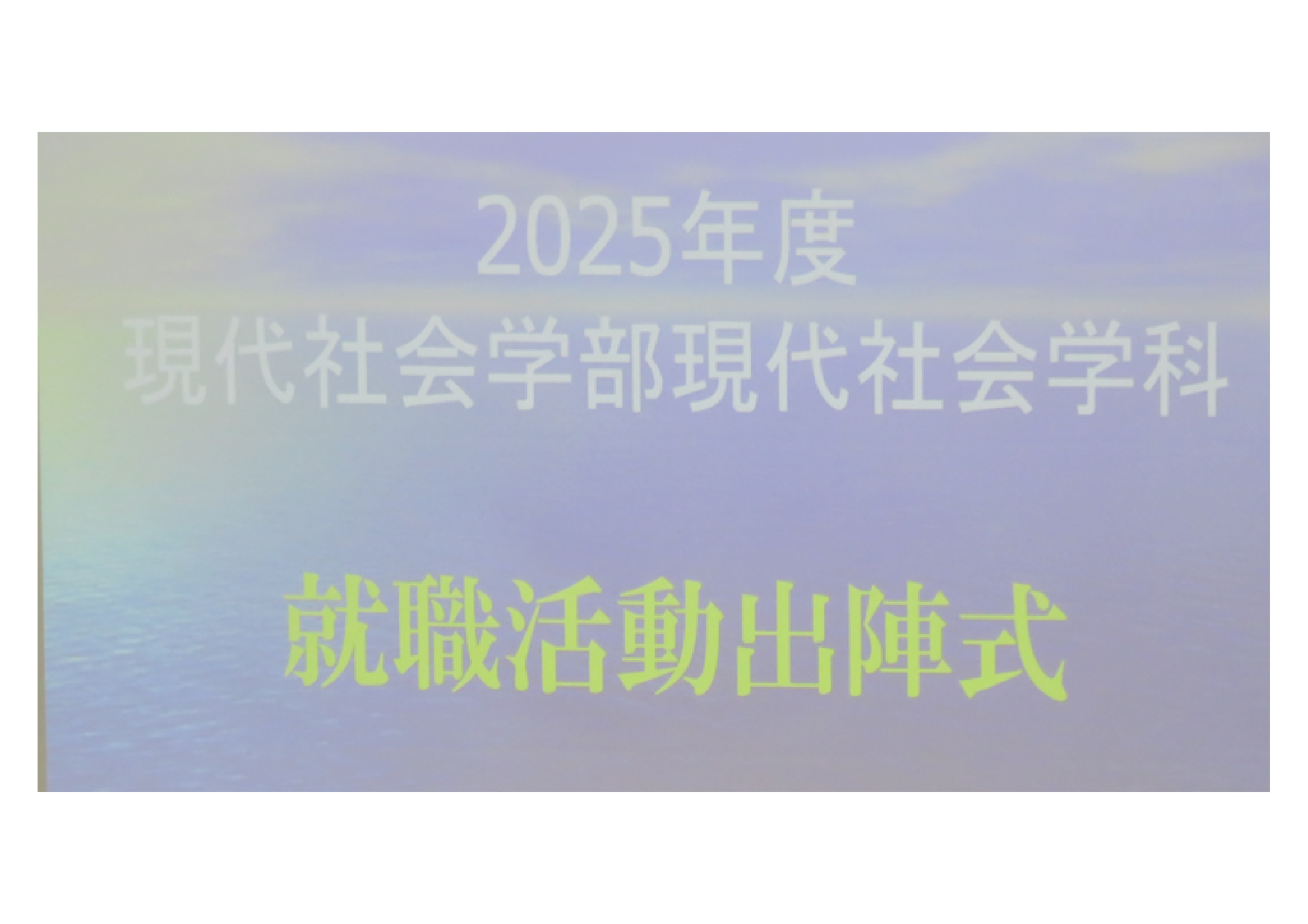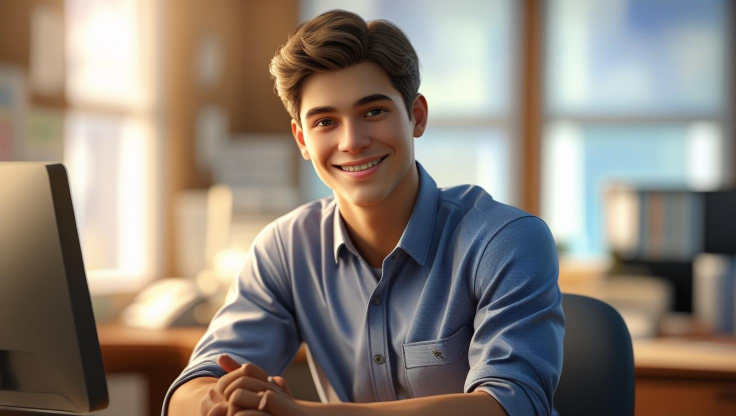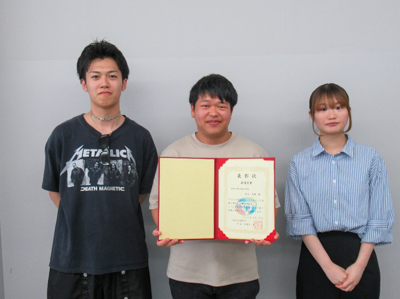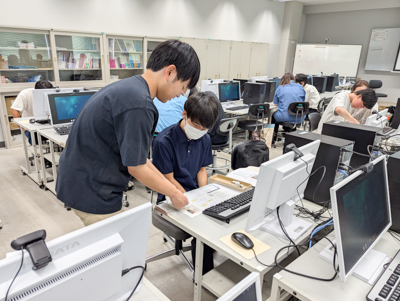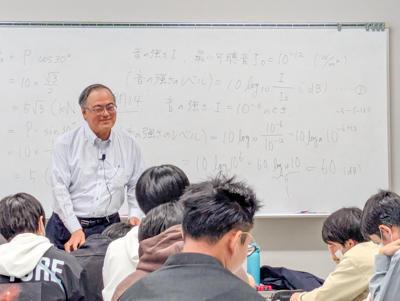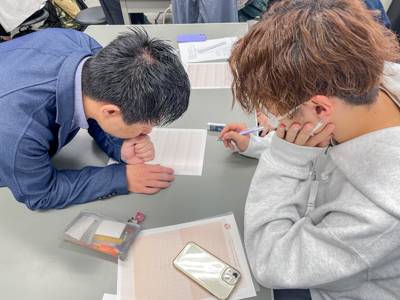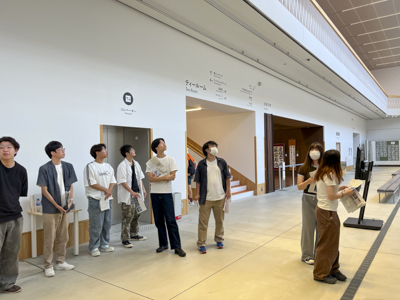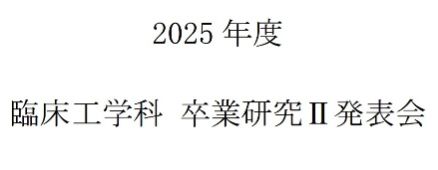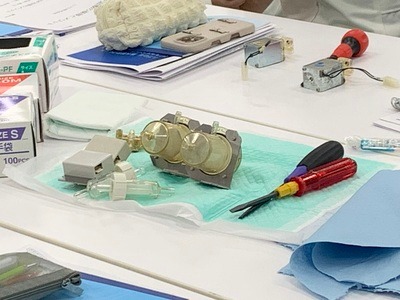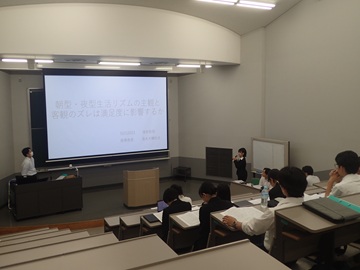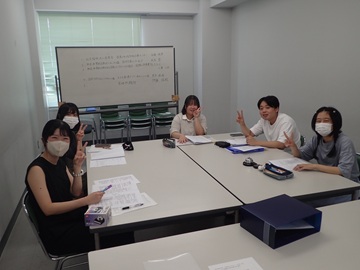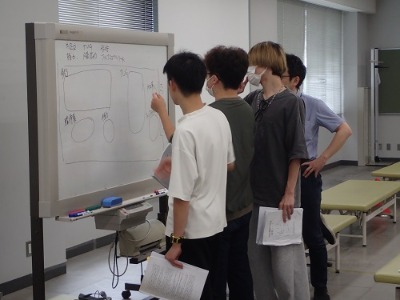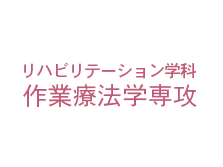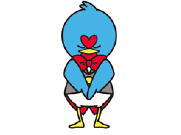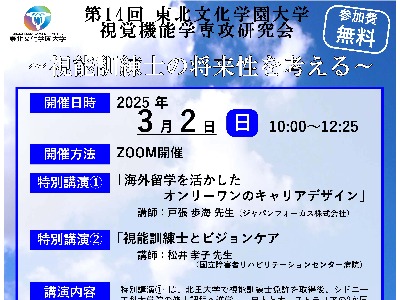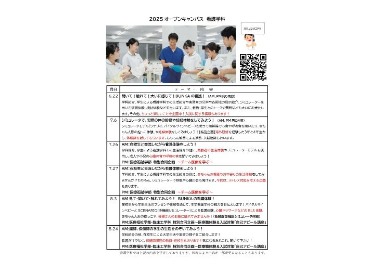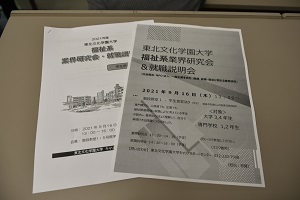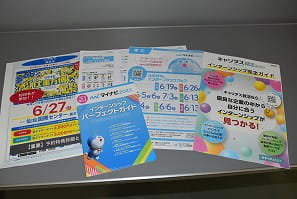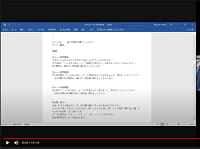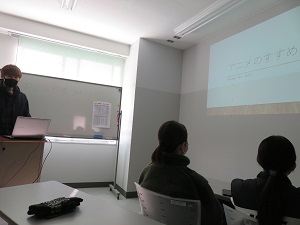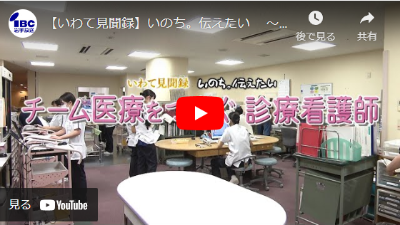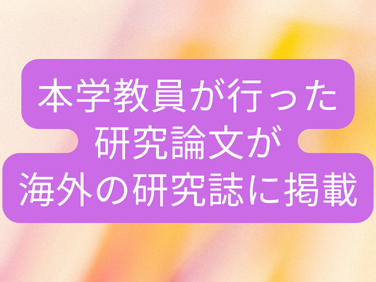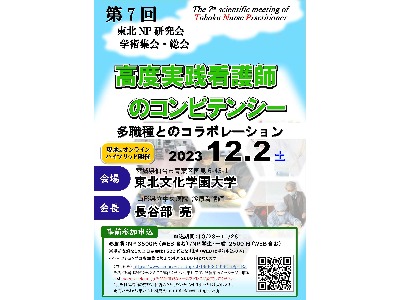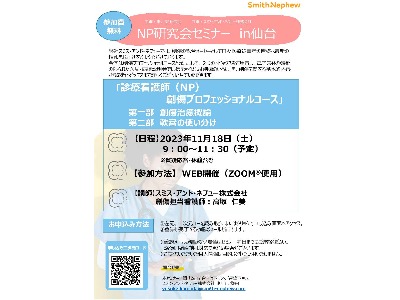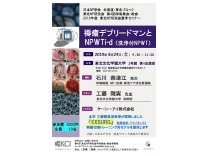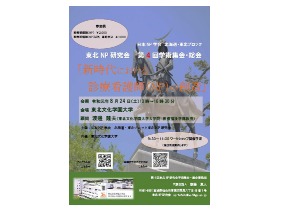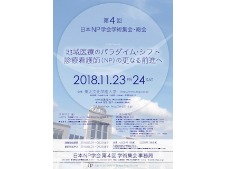身体機能評価の学び(評価学実習Ⅰ):2年生
作業療法学専攻
2年生は今年の4月から「評価学実習Ⅰ」の授業で身体機能を評価するための検査を多く学んでいます。
例えば、筋力検査、感覚検査、手指の検査、バランスの検査などです。

(筋力検査)

(バランス検査)
これらの検査の方法は教科書や検査の手引き(説明書)に記載されているため、学生同士で読み合わせることである程度の実施ができます。
手指の検査に重点を置いて実践
今回は特に手指の検査に重点を置きました。学生がグループごとに「作業療法士役」と「患者さん役」に分かれてみんなの前で実演をしました。


(大きさや材質の異なる物体を制限時間内に運ぶことができるか、分かりやすく患者さん役に伝えます)
実演後に教員から補足説明をし、それぞれの検査が日常生活の中でどのような意味を持つのか、どのように応用されるのか確認をしました。
この授業を通して
?検査の正確な実施
?動作の観察力
?患者さんが安心できる声掛けや説明の方法
?日常生活(作業)の困難さを想定し、支援する方法
などを学ぶことができたのではないかと思います。
特に日常生活(作業)の困難さを想定することは作業療法士にとって重要ですね。
例えば、筋力検査、感覚検査、手指の検査、バランスの検査などです。

(筋力検査)

(バランス検査)
これらの検査の方法は教科書や検査の手引き(説明書)に記載されているため、学生同士で読み合わせることである程度の実施ができます。
手指の検査に重点を置いて実践
今回は特に手指の検査に重点を置きました。学生がグループごとに「作業療法士役」と「患者さん役」に分かれてみんなの前で実演をしました。


(大きさや材質の異なる物体を制限時間内に運ぶことができるか、分かりやすく患者さん役に伝えます)
実演後に教員から補足説明をし、それぞれの検査が日常生活の中でどのような意味を持つのか、どのように応用されるのか確認をしました。
この授業を通して
?検査の正確な実施
?動作の観察力
?患者さんが安心できる声掛けや説明の方法
?日常生活(作業)の困難さを想定し、支援する方法
などを学ぶことができたのではないかと思います。
特に日常生活(作業)の困難さを想定することは作業療法士にとって重要ですね。